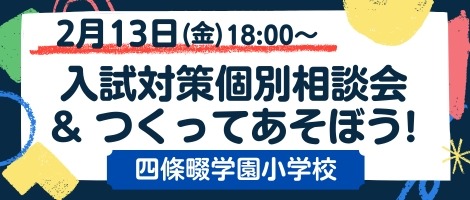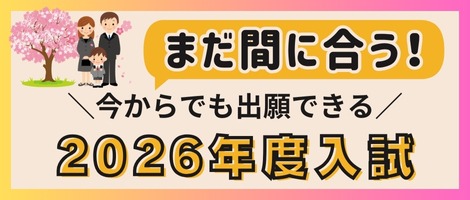小林聖心女子学院小学校
英語の教育課程特例校に兵庫県で初認定。12年一貫で育む 小林聖心の“伝える力”
グローバル化が進む中、小学校からの英語教育への関心は年々高まっています。2025年度より兵庫県内の私立中学で初めて「英語教育課程特例校」に認定された小林聖心女子学院小学校では、同校が長年にわたり取り組んできた小学校から高校までの12年間一貫教育ならではの英語教育の実績があります。
英語を知識として習得するだけでなく、自分の思いや文化を伝える“ツール”として育てる独自のカリキュラムについて副校長の藤本雅司先生、英語専科の間森圭以子先生、ネイティブ教師のNancy Shiosaki先生にお話を伺いました。
英語教育課程特例校としての指定。12年一貫の英語カリキュラムの伝統と実績
2025年度、小林聖心女子学院小学校は、文部科学省より英語の「教育課程特例校」の指定を受けました。これは、通常の学習指導要領の枠を超え、各校の教育理念に基づいた特別なカリキュラム編成が認められる制度で、兵庫県内の私立小学校では初の指定となります。
同校は、小学校から高校までの12年間一貫教育を行う中で、「魂を育てる」「知性を磨く」「実行力を養う」という3本柱を掲げています。自分を大切にしながらも世界に視野を広げ、これからのグローバル社会を生き抜く資質・能力を養う教育を実践してきました。
英語教育においては、国境を越えて他者のために行動できるよう、“他者”とつながる手段となる英語力を養う独自のカリキュラムが編成されています。
小林聖心の英語教育は、児童の発達段階に応じて段階的にステップアップしていきます。小学校1〜4年では、歌やチャンツを通して自然と英語の音やリズムに親しみ、英語の土台を育てます。5年生〜中学2年生では、文法学習も始まり英語を使って身近な話題に関する言語活動を積み重ね、中学3年〜高校3年では、多様な表現や語彙を用いたディベート・ディスカッションへと発展していきます。長期的な視点で「使える英語力」を育て、英語を使って人や社会のために役立つ人に育つことを目指しています。
副校長の藤本雅司先生は、「12年間の流れの中で、英語を道具として活用できる段階まで育てていくのが私たちの目標です。今回の特例校指定は、これまでの学院の英語教育の実績が評価されたことでもあり、今後はその成果を広く社会に発信していく責任も感じています」と語ります。
同校は、小学校から高校までの12年間一貫教育を行う中で、「魂を育てる」「知性を磨く」「実行力を養う」という3本柱を掲げています。自分を大切にしながらも世界に視野を広げ、これからのグローバル社会を生き抜く資質・能力を養う教育を実践してきました。
英語教育においては、国境を越えて他者のために行動できるよう、“他者”とつながる手段となる英語力を養う独自のカリキュラムが編成されています。
小林聖心の英語教育は、児童の発達段階に応じて段階的にステップアップしていきます。小学校1〜4年では、歌やチャンツを通して自然と英語の音やリズムに親しみ、英語の土台を育てます。5年生〜中学2年生では、文法学習も始まり英語を使って身近な話題に関する言語活動を積み重ね、中学3年〜高校3年では、多様な表現や語彙を用いたディベート・ディスカッションへと発展していきます。長期的な視点で「使える英語力」を育て、英語を使って人や社会のために役立つ人に育つことを目指しています。
副校長の藤本雅司先生は、「12年間の流れの中で、英語を道具として活用できる段階まで育てていくのが私たちの目標です。今回の特例校指定は、これまでの学院の英語教育の実績が評価されたことでもあり、今後はその成果を広く社会に発信していく責任も感じています」と語ります。

副校長 藤本雅司先生

少人数で丁寧に―英語が自然に身につく仕組み
4-4-4制カリキュラムのうち「StageⅠ」にあたる小学校1〜4年生においては、週2時間の英語学習を実施。各クラスを2つに分け、ネイティブ教員と日本人教員がそれぞれ担当する「スプリット授業」を取り入れ、少人数で丁寧な指導が行われています。これにより、発音や語彙といった基礎だけでなく、「聞く・話す」力とともに、英語に対する“自信”も自然と育まれていきます。
英語教諭の間森圭以子先生は、「1年生では“先生の口の動きをしっかり見る”ことから始まります。耳だけでなく、目と体で英語を感じ取る習慣をつけています」と話します。またネイティブの先生と日本人の先生が交代で授業を行うスプリット授業は、少人数で行われるため、発音や理解度に対する丁寧なフォローが可能です。
また、音と文字の関係を学ぶ「フォニックス指導」も伝統的に実施されており、朝の時間を活用して音声の習得が「読む・書く」へとつながるように設計された、体系的な英語学習が組み込まれています。児童は毎朝、英語の音に自然に触れながら、体感としての言語感覚を育んでいきます。
英語教諭の間森圭以子先生は、「1年生では“先生の口の動きをしっかり見る”ことから始まります。耳だけでなく、目と体で英語を感じ取る習慣をつけています」と話します。またネイティブの先生と日本人の先生が交代で授業を行うスプリット授業は、少人数で行われるため、発音や理解度に対する丁寧なフォローが可能です。
また、音と文字の関係を学ぶ「フォニックス指導」も伝統的に実施されており、朝の時間を活用して音声の習得が「読む・書く」へとつながるように設計された、体系的な英語学習が組み込まれています。児童は毎朝、英語の音に自然に触れながら、体感としての言語感覚を育んでいきます。

英語専科 間森圭以子先生

英語で“思いを伝える力”を育むステージへ
StageⅡ(5〜8年生)以降では、「読む・書く」の力も加わり、英語での発信力が育まれていきます。会話表現を、真似て言うだけ、覚えるだけ、では物足りなくなり、「理由を知りたい」と思うようになるこの学齢期に、中学校の教科書「New Treasure」を使った文法指導が始まります。ステージ1で自然に耳にし、口にした英語表現の 文構造を理解することで、正確な英文を書く力と読む力、より正確な発音が養われ、より確かな発信力の基礎を固めます。特にプレゼンテーションスキル(PVS)の育成に力を入れており、4年生からは英語発表会、5年生では100語程度の暗唱、6年生ではフィリピンの姉妹校とオンライン国際交流を実施。「日本文化を英語で伝える」というテーマのもと、アニメや食文化など、子どもたち自身が関心のある話題を選び、表現していきます。
ネイティブ教員のNancy Shiosaki先生は、「英語はあくまで“道具”です。子どもたちが将来、自分の思いや日本の文化を世界に発信するための基盤を、小学校でしっかり育てたい」と語ります。
ネイティブ教員のNancy Shiosaki先生は、「英語はあくまで“道具”です。子どもたちが将来、自分の思いや日本の文化を世界に発信するための基盤を、小学校でしっかり育てたい」と語ります。

ネイティブ教師 Nancy Shiosaki先生

誰もが英語に自信を持てるサポート体制
小林聖心の英語教育は、英語に初めて触れる子どもも、経験のある子どもも、どちらも安心して学べる環境が整っています。一人ひとりの理解度に応じた少人数での授業や、丁寧なサポート体制により、自信をもって英語に取り組めるようになります。最近では、インターナショナル系幼稚園から入学する子どもも見られますが、どの子にとっても、それぞれのペースで無理なく力を伸ばせることが大きな魅力です。
「クラスを2つに分けて少人数で行うスプリット授業では、子どもたちの特性や成長に応じた丁寧なサポートが可能です。発音も一人ひとりしっかり聞き取って指導が可能です」と間森先生。英語をすでに話せる子どもには発展的な学びを、初めて英語に触れる子どもには基礎から丁寧に学習します。
また、英語力の成果を発表する場として、学年ごとの発表会やスピーチ大会もあり、子どもたちはチャレンジを通して、自然と“人前で英語を話す”ことへの抵抗感が薄れていきます。誰ひとり取り残さない姿勢が、小林聖心の英語教育の根幹にあります。
「クラスを2つに分けて少人数で行うスプリット授業では、子どもたちの特性や成長に応じた丁寧なサポートが可能です。発音も一人ひとりしっかり聞き取って指導が可能です」と間森先生。英語をすでに話せる子どもには発展的な学びを、初めて英語に触れる子どもには基礎から丁寧に学習します。
また、英語力の成果を発表する場として、学年ごとの発表会やスピーチ大会もあり、子どもたちはチャレンジを通して、自然と“人前で英語を話す”ことへの抵抗感が薄れていきます。誰ひとり取り残さない姿勢が、小林聖心の英語教育の根幹にあります。

国際理解教育を通じて、「世界の中の自分」を育てる12年間
12年一貫の英語教育カリキュラムの中で、子どもたちは自分の考えを深め、他者とつながり、やがて社会に貢献する力を身につけていきます。
小学校高学年では広島や白川郷を訪れ、日本の文化や歴史を学ぶ宿泊学習を実施しています。卒業生の多くが「日本文化を深く学んだからこそ、異文化理解の大切さに気づいた」と話すそうです。英語教育は、異文化を理解するだけでなく、自分自身や自国の文化を見つめ直すきっかけにもなっています。小林聖心が掲げる「魂を育てる」、「知性を磨く」、「実行力を養う」という教育方針のもと、英語教育もまた“生きる力”を育む重要な柱となっています。
藤本副校長はこう締めくくります。
「英語を学ぶことで、子どもたちは自分自身や日本の文化を改めて見つめ直すようになります。それが、世界を知ることにもつながっていく。英語はあくまで“手段”であり、大切なのは、その先にある“思い”をどう届けていくか。その力をここで育てていきたいのです」
小学校高学年では広島や白川郷を訪れ、日本の文化や歴史を学ぶ宿泊学習を実施しています。卒業生の多くが「日本文化を深く学んだからこそ、異文化理解の大切さに気づいた」と話すそうです。英語教育は、異文化を理解するだけでなく、自分自身や自国の文化を見つめ直すきっかけにもなっています。小林聖心が掲げる「魂を育てる」、「知性を磨く」、「実行力を養う」という教育方針のもと、英語教育もまた“生きる力”を育む重要な柱となっています。
藤本副校長はこう締めくくります。
「英語を学ぶことで、子どもたちは自分自身や日本の文化を改めて見つめ直すようになります。それが、世界を知ることにもつながっていく。英語はあくまで“手段”であり、大切なのは、その先にある“思い”をどう届けていくか。その力をここで育てていきたいのです」
取材を終えて
グローバル化が加速するいま、「英語を使って何ができるか」が問われる時代に入りました。国際社会で活躍するためには、語彙や文法の知識だけでなく、自分の思いを相手に伝え、異なる文化と向き合う力が必要です。小林聖心女子学院では、そうした“実践的な英語力”を、小学校から高校までの12年間で一貫して育む環境が整えられていました。
特に印象的だったのは、先生方が皆さん、口をそろえて言われる「英語は手段であり、誰かとつながり、思いを伝える力」という言葉。英語をただ学ぶのではなく、誰かとつながり、社会の役に立つための“言葉の力”として位置づけられている点に、カトリック教育の哲学を感じました。
特に印象的だったのは、先生方が皆さん、口をそろえて言われる「英語は手段であり、誰かとつながり、思いを伝える力」という言葉。英語をただ学ぶのではなく、誰かとつながり、社会の役に立つための“言葉の力”として位置づけられている点に、カトリック教育の哲学を感じました。