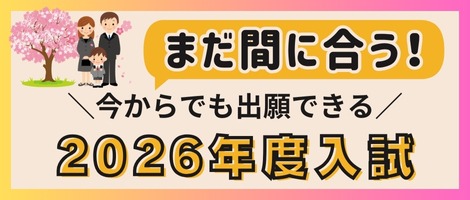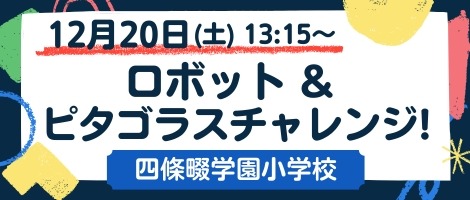箕面自由学園小学校
児童の未来を拓く100年!箕面自由学園小学校が実践する、少人数教育と「五感で学ぶ」体験の力
今年100周年を迎える箕面自由学園。1926年の開校から男女共学で、外国人の英語の先生による英語教育を導入するなど、当時としては非常に先進的な学校でした。昔も今も変わらないところは、体験教育を脈々と受け継いでいるところ。『体験と実践』を根幹とした学園の歩みについて、教頭の三宅先生と児童のみなさんの声から、学園の教育の真髄に迫ります。
箕面自由学園小学校 教頭 三宅理磨先生、児童のみなさんのお話
箕面自由学園小学校 教頭 三宅理磨先生、児童のみなさんのお話

教頭 三宅理磨先生
箕面自由学園小学校 教頭 三宅理磨先生のお話
時代を超えて受け継がれる親の願い
1926年、大阪の北摂地域に住宅が増え始めた頃、この地に住む保護者たちは「近くに子どもを通わせられる小学校を作りたい」という強い思いから資金を出し合い、箕面自由学園を創立しました。100年の時を経て、当時の保護者はどのような教育を望んでいたのでしょうか。三宅先生は次のように語ります。
「最近の記事を読むと、現代は大正時代に少し似ているという記述があります。第一次世界大戦後の特需はあったものの、経済的に厳しい中、関東大震災が起こり、自然災害や経済など、さまざまな不安が渦巻いていました。社会の大きな変革期であり、それまでの道徳観が揺らぎ始めた時代です。そのような中で学校が建設されたのは、現在の考え方と共通する部分が多かったと思います。昔も今の保護者も、我が子には幸せになってほしい、経済的な余裕や技術力、知識も身につけて欲しいと願ったのではないでしょうか。机上の学問だけでは得られないものがあるという考えのもとに成り立ったのが箕面自由学園です」
「最近の記事を読むと、現代は大正時代に少し似ているという記述があります。第一次世界大戦後の特需はあったものの、経済的に厳しい中、関東大震災が起こり、自然災害や経済など、さまざまな不安が渦巻いていました。社会の大きな変革期であり、それまでの道徳観が揺らぎ始めた時代です。そのような中で学校が建設されたのは、現在の考え方と共通する部分が多かったと思います。昔も今の保護者も、我が子には幸せになってほしい、経済的な余裕や技術力、知識も身につけて欲しいと願ったのではないでしょうか。机上の学問だけでは得られないものがあるという考えのもとに成り立ったのが箕面自由学園です」
少人数教育だからできる『体験と実践』
箕面自由学園の大きな特徴は、少人数教育を活かした豊富な学校行事です。デジタル化が進む現代においても、建学の精神にある『体験と実践』を通して人との関わりや学ぶ楽しさを身につけることは、人間の確固たる土台となり、将来にわたって普遍的な価値を持つと考えています。
「バーチャルの世界での疑似体験は、行った気分にはなれても心に残りません。児童の心に残るにはどうしたらよいか。そのきっかけを作るのが私たち教員の重要な役割です。初めての経験を五感で楽しむのはもちろん、一人ではなく周りの人と関わる行事にすることで、最終的には自分の在り方を見つめ直す機会となります」と三宅先生は語ります。
「バーチャルの世界での疑似体験は、行った気分にはなれても心に残りません。児童の心に残るにはどうしたらよいか。そのきっかけを作るのが私たち教員の重要な役割です。初めての経験を五感で楽しむのはもちろん、一人ではなく周りの人と関わる行事にすることで、最終的には自分の在り方を見つめ直す機会となります」と三宅先生は語ります。
心を動かす体験と成長
5年生で行われる社会科の農業学習プログラムには、1泊2日の「ふるさと体験学校」があります。「田植え」と「稲刈り」の時期に年2回、同じ場所を訪れ、農家のご家庭にお世話になりながら様々なことを学びます。
「初めてお会いする方々にも臆することなく、失敗してもいいからと前向きに飛び込んでいく度胸と勇気が、本学園の児童の特徴です。もちろん叱られることもあるかもしれませんが、それら全てが児童にとっては心を動かされる行事となっています。宿泊先では、農業について丁寧に教えてくださり、また、ご自身の仕事への誇りや情熱を込めて語ってくれます。児童たちにとっても、本当に豊かな時間を過ごせるひとときとなっています。想像以上の失敗や経験が、児童にとって心に残る体験となっています」と三宅先生。
全ての行事は基本的に、以前児童が経験したことのある場所はできるだけ避け、新しい場所が選ばれています。水辺や山など、豊かな自然の中で五感を使い、体を動かす喜びを知ります。行事の時の児童は、本当に楽しそうな表情ですと、三宅先生は嬉しそうに話します。100年前は簡単にできたような自然体験も、今では時間や準備が必要で、なかなか難しくなっており、それを学校が行うところが、この学園の良さだと三宅先生は語ります。
「初めてお会いする方々にも臆することなく、失敗してもいいからと前向きに飛び込んでいく度胸と勇気が、本学園の児童の特徴です。もちろん叱られることもあるかもしれませんが、それら全てが児童にとっては心を動かされる行事となっています。宿泊先では、農業について丁寧に教えてくださり、また、ご自身の仕事への誇りや情熱を込めて語ってくれます。児童たちにとっても、本当に豊かな時間を過ごせるひとときとなっています。想像以上の失敗や経験が、児童にとって心に残る体験となっています」と三宅先生。
全ての行事は基本的に、以前児童が経験したことのある場所はできるだけ避け、新しい場所が選ばれています。水辺や山など、豊かな自然の中で五感を使い、体を動かす喜びを知ります。行事の時の児童は、本当に楽しそうな表情ですと、三宅先生は嬉しそうに話します。100年前は簡単にできたような自然体験も、今では時間や準備が必要で、なかなか難しくなっており、それを学校が行うところが、この学園の良さだと三宅先生は語ります。


第一次産業に触れる重要性
「昨今、第一次産業は日本において衰退傾向にあります。これからは、食について真剣に考えなければならない時代に突入する中で、実際に自然に触れ、一次産業を体験することは、将来、社会に出る上で重要な示唆を与えます」
三宅先生は続けます。
「AIやICTは非常に便利で、これからは必要になってくるものなので、うまく取り入れなければなりません。しかし、ウェブで得た知識は残りづらく、通り過ぎてしまいます。人間本来の力を伸ばすためには、やはり人との関わりや実体験を通して心を動かす経験が不可欠です。小学校の6年間での経験は、子どもたちが未来を生き抜く力を育む上で非常に重要だと考えています」と述べました。
三宅先生は続けます。
「AIやICTは非常に便利で、これからは必要になってくるものなので、うまく取り入れなければなりません。しかし、ウェブで得た知識は残りづらく、通り過ぎてしまいます。人間本来の力を伸ばすためには、やはり人との関わりや実体験を通して心を動かす経験が不可欠です。小学校の6年間での経験は、子どもたちが未来を生き抜く力を育む上で非常に重要だと考えています」と述べました。

少人数教育が育むコミュニケーション能力
数多くの体験型行事が実施できるのは、1学年50人を2クラスに分けた少人数教育だからこそです。児童の安全面が考慮でき、先生の目も行き届く人数だからこそ成り立っています。学習面では対話の多さが国語力アップの根本になっており、家庭だけではなく、学校での先生との対話や児童同士の対話が多ければ多いほど、国語力に繋がっています。少人数だからこそ、担任、副担任、教科ごとの先生など、様々な先生が関わることができ、多角的な対話も増えます。このコミュニケーションの量こそが、見知らぬ人との対話にも飛び込んでいける児童を育てています。
例えば、生成AIに悩み相談をして回答が得られることもあるでしょう。しかし、もしそれを人に話せていたら、もっと違う答えが出てきたかもしれません。相談相手からの回答に対して、自分の中で考え、会話を続けていく力を持てるような子どもたちに育ってほしいと願っています。結局AIは、私たちの様々なデータを蓄積しているに過ぎません。それ以上のことを考えられる子どもに育ってもらうことが、今後先行き不透明と言われる未来に向かう児童たちには必要だと思います。それは機械と人間ではなく、やはり人間と人間の中で育つ部分です。
「そういったことも含め、2、3年生、4、5年生でペアになり、宿泊行事が行われます。日常の活動でも、スキー班や宿泊部屋は異学年での縦割りです。教員が何人も集まって時間をかけて班員を決めます。児童からは「どうやって決めたの?」と聞かれることもありますが、「色々考えて決めたから、まずは一度やってみてほしい」と伝えると、最初は距離を置きながらも、活動を良いものにしようとお互いに歩み寄る姿が見られます。そういったきっかけがあると、人は成長します。児童期の一年間は非常に長く、日々の体験が重要です。一度きりの経験ではなく、繰り返し同じ活動を行うことで、子どもたちの意識は大きく変わります。『蟻の目と鳥の目』、上級生には全体を俯瞰し、下級生を導く力を(鳥の目)、下級生には上級生の行動から学ぶ姿勢を促します(蟻の目)。こうした段階的な成長を経て、高学年になると、受験や進学といった物事にも泰然自若と向き合える児童へと成長します」と三宅先生は語られました。
例えば、生成AIに悩み相談をして回答が得られることもあるでしょう。しかし、もしそれを人に話せていたら、もっと違う答えが出てきたかもしれません。相談相手からの回答に対して、自分の中で考え、会話を続けていく力を持てるような子どもたちに育ってほしいと願っています。結局AIは、私たちの様々なデータを蓄積しているに過ぎません。それ以上のことを考えられる子どもに育ってもらうことが、今後先行き不透明と言われる未来に向かう児童たちには必要だと思います。それは機械と人間ではなく、やはり人間と人間の中で育つ部分です。
「そういったことも含め、2、3年生、4、5年生でペアになり、宿泊行事が行われます。日常の活動でも、スキー班や宿泊部屋は異学年での縦割りです。教員が何人も集まって時間をかけて班員を決めます。児童からは「どうやって決めたの?」と聞かれることもありますが、「色々考えて決めたから、まずは一度やってみてほしい」と伝えると、最初は距離を置きながらも、活動を良いものにしようとお互いに歩み寄る姿が見られます。そういったきっかけがあると、人は成長します。児童期の一年間は非常に長く、日々の体験が重要です。一度きりの経験ではなく、繰り返し同じ活動を行うことで、子どもたちの意識は大きく変わります。『蟻の目と鳥の目』、上級生には全体を俯瞰し、下級生を導く力を(鳥の目)、下級生には上級生の行動から学ぶ姿勢を促します(蟻の目)。こうした段階的な成長を経て、高学年になると、受験や進学といった物事にも泰然自若と向き合える児童へと成長します」と三宅先生は語られました。

峯砂さん(4年生)、辻さん(5年生)、浦川さん(6年生)にインタビュー
〈学校での日々を振り返って、特に思い出に残っている体験活動を教えてください〉
峯砂さん(4年生):社会科見学の「暮らしとスーパーマーケットの仕事」が印象的でした。普段は何も考えずに「あれ買って!これ買って!」と言っていましたが、店員さんに働く時に気をつけていることや、魚の値段はどう決めているのかなど、普段は聞くことができない質問をすると、スーパーマーケットの裏側を学べ、本当にたくさんの発見がありました。私たちのために一生懸命働いてくれている店員さんには感謝の気持ちでいっぱいになりました。
辻さん(5年生): 1年生の時の「なかよし体験学校」が、最高に心に残っています。みんなで布団を敷いて、和室での寝泊まりが「楽しい」の一言。友達と一緒に泊まるのが新鮮で、全く緊張せず、めちゃくちゃ楽しかったです。魚釣りも、釣れた時は「やったー」という感じで心に残るいい思い出になりました。
浦川さん(6年生): 私は、スキー学校です。家でもスキーに行ったことがなく、最初は全く滑ることができず、初級コースでしたが、たった1年で上級コースも滑ることができるようになりました。自分でも「え!? ほんまに?」と驚きで、心身ともに成長できて本当に嬉しかったです。
峯砂さん(4年生):社会科見学の「暮らしとスーパーマーケットの仕事」が印象的でした。普段は何も考えずに「あれ買って!これ買って!」と言っていましたが、店員さんに働く時に気をつけていることや、魚の値段はどう決めているのかなど、普段は聞くことができない質問をすると、スーパーマーケットの裏側を学べ、本当にたくさんの発見がありました。私たちのために一生懸命働いてくれている店員さんには感謝の気持ちでいっぱいになりました。
辻さん(5年生): 1年生の時の「なかよし体験学校」が、最高に心に残っています。みんなで布団を敷いて、和室での寝泊まりが「楽しい」の一言。友達と一緒に泊まるのが新鮮で、全く緊張せず、めちゃくちゃ楽しかったです。魚釣りも、釣れた時は「やったー」という感じで心に残るいい思い出になりました。
浦川さん(6年生): 私は、スキー学校です。家でもスキーに行ったことがなく、最初は全く滑ることができず、初級コースでしたが、たった1年で上級コースも滑ることができるようになりました。自分でも「え!? ほんまに?」と驚きで、心身ともに成長できて本当に嬉しかったです。

峯砂さん(4年生)

なかよし体験学校
〈素晴らしい体験ばかりですね。そういった行事や体験を通して、何か壁を乗り越えたり、学んだりしたことはありますか?〉
峯砂さん:1年生の時の宿泊で、布団を敷く際に、「一人でやりたい」という意見と、「みんなで協力してやりたい」と意見が食い違うことがありました。どうなるかヒヤヒヤでしたが、最終的には乗り越えることができました。2年生では、相手の意見を尊重し、言葉遣いを意識するように心がけるなど、友達と協力することの大切さを学びました。
辻さん:1年生、2年生、3年生と同じ場所に宿泊体験で行きましたが、3年生の時に班長になりました。みんなが安全に過ごせるように気を配るのが大変でした。上級生になることで役割が変わり、みんなをまとめることができた達成感が残っています。
浦川さん:6年生の運動会の練習の時、難しい演技などみんなの息が合わなくて大変でした。どうしようかと考えた時、特に最上級生として、下級生にアドバイスをし、「こうしようね」「楽しめるようにしようね」と声を掛け合うことを意識することで、揃うようになりました。お互いが協力することや、諦めずに続けることは、本当に大切だと身をもって感じました。
峯砂さん:1年生の時の宿泊で、布団を敷く際に、「一人でやりたい」という意見と、「みんなで協力してやりたい」と意見が食い違うことがありました。どうなるかヒヤヒヤでしたが、最終的には乗り越えることができました。2年生では、相手の意見を尊重し、言葉遣いを意識するように心がけるなど、友達と協力することの大切さを学びました。
辻さん:1年生、2年生、3年生と同じ場所に宿泊体験で行きましたが、3年生の時に班長になりました。みんなが安全に過ごせるように気を配るのが大変でした。上級生になることで役割が変わり、みんなをまとめることができた達成感が残っています。
浦川さん:6年生の運動会の練習の時、難しい演技などみんなの息が合わなくて大変でした。どうしようかと考えた時、特に最上級生として、下級生にアドバイスをし、「こうしようね」「楽しめるようにしようね」と声を掛け合うことを意識することで、揃うようになりました。お互いが協力することや、諦めずに続けることは、本当に大切だと身をもって感じました。

浦川さん(6年生)

運動会
〈辻さんと浦川さんは、オーストラリアでの国際交流体験にも参加されたそうですね。どうでしたか?〉
辻さん: 面白かったのは、自然がいっぱいあるところです。「え、これ何!?」と思うようなヤシの実が落ちていたり、お邪魔なへんてこな鳥がいたり、夜になったらネズミが出てきたりして、日本とは全然違う環境に「うわー、すごい」と驚きました。ホストファミリーとのコミュニケーションは、電子辞書を使いながらたくさん話すことができました。
浦川さん:私も全然不安はなく、ありのまま飛び込みました。
〈印象的なエピソードはありますか?〉
辻さん:ホストファミリーに海に連れて行ってもらいました。みんなでフィッシュアンドチップスを食べに行った時に、僕がものすごくたくさん食べたことです(笑)。「え、そんなに食べるの?」と、みんなびっくりしていました。オーストラリアで誕生日を迎え、学校でみんなに祝ってもらえたのが、すごく嬉しかったです。
浦川さん:私は映画館へ連れて行ってもらいました。食事もラーメンやカレーなど日本食も作ってくれたので、食事に困ることはありませんでした。楽しかったことは、学校でみんなでお昼ご飯を食べられたことでした。
〈日本の文化を伝えるミッションもあったと聞きました〉
辻さん・浦川さん:日本の文化を伝えるミッションがあり、薄く切った発泡スチロールに糸を巻き付けて作った凧を上げたり、習字を教えたり、兜を作ったりと日本の伝統文化を伝える交流ができたのは楽しい思い出です。
辻さん: 面白かったのは、自然がいっぱいあるところです。「え、これ何!?」と思うようなヤシの実が落ちていたり、お邪魔なへんてこな鳥がいたり、夜になったらネズミが出てきたりして、日本とは全然違う環境に「うわー、すごい」と驚きました。ホストファミリーとのコミュニケーションは、電子辞書を使いながらたくさん話すことができました。
浦川さん:私も全然不安はなく、ありのまま飛び込みました。
〈印象的なエピソードはありますか?〉
辻さん:ホストファミリーに海に連れて行ってもらいました。みんなでフィッシュアンドチップスを食べに行った時に、僕がものすごくたくさん食べたことです(笑)。「え、そんなに食べるの?」と、みんなびっくりしていました。オーストラリアで誕生日を迎え、学校でみんなに祝ってもらえたのが、すごく嬉しかったです。
浦川さん:私は映画館へ連れて行ってもらいました。食事もラーメンやカレーなど日本食も作ってくれたので、食事に困ることはありませんでした。楽しかったことは、学校でみんなでお昼ご飯を食べられたことでした。
〈日本の文化を伝えるミッションもあったと聞きました〉
辻さん・浦川さん:日本の文化を伝えるミッションがあり、薄く切った発泡スチロールに糸を巻き付けて作った凧を上げたり、習字を教えたり、兜を作ったりと日本の伝統文化を伝える交流ができたのは楽しい思い出です。
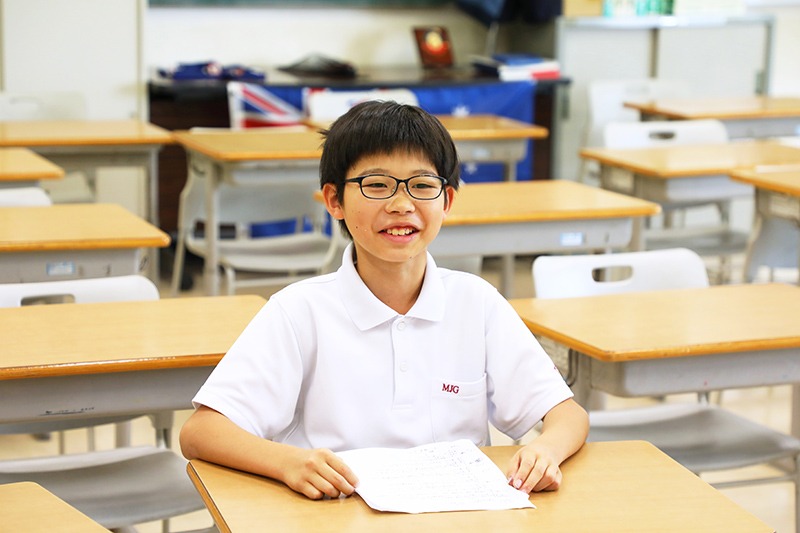
辻さん(5年生)

オーストラリア体験学校
〈小学校受験を控えている方へメッセージをお願いします〉
浦川さん:箕面自由学園小学校は、幼稚園から高校まで交流が盛んで、みんなすごく仲良しです。校長先生のお話もすごく面白くて眠くなりません(笑)。運動会では吹奏楽の演奏があったり、1、2年生のダンスに中高のダンス部が参加してくれたり、チアリーダー部の演技もあり、とても楽しい運動会になりました。「え、他の学校でこんなことある?」と思うような、魅力的な行事が本当にたくさんあります。ぜひ箕面自由学園に来てください。
浦川さん:箕面自由学園小学校は、幼稚園から高校まで交流が盛んで、みんなすごく仲良しです。校長先生のお話もすごく面白くて眠くなりません(笑)。運動会では吹奏楽の演奏があったり、1、2年生のダンスに中高のダンス部が参加してくれたり、チアリーダー部の演技もあり、とても楽しい運動会になりました。「え、他の学校でこんなことある?」と思うような、魅力的な行事が本当にたくさんあります。ぜひ箕面自由学園に来てください。
まとめ
毎年ユニークな取り組みをされている箕面自由学園ですが、100周年を迎えて、変わることなく受け継がれた「体験と実践」の話を伺う中で、先生方の熱い思いがひしひしと伝わってきます。聞けば聞くほど、学園の教育の最も大切な部分が詰まっていると感じます。時代に合わせて変わる部分と、残す根幹の部分がしっかり確立しており、時を経ても児童の心と体に深く刻まれ、未来へ確実に繋がるかけがえのない財産となっている様子がわかります。インタビューに応じてくれた児童のみなさんはとてもフレンドリー。話しかけるとすぐにざっくばらんに答えてくれ、明るく飾らない様子が非常に印象的でした。彼らの生き生きとした表情や率直な言葉からは、学園での充実した日々が伝わってきます。ぜひ一度学校の雰囲気に触れてみてはいかがでしょうか。