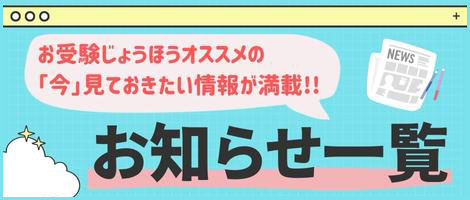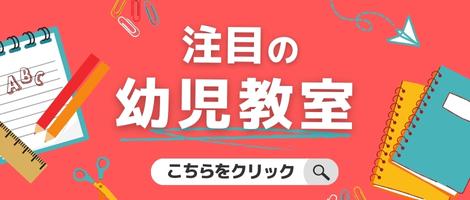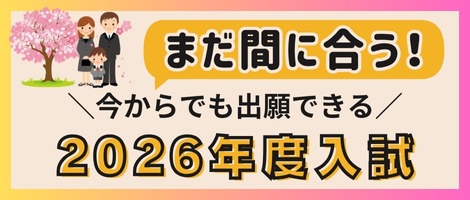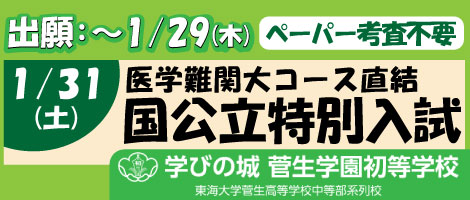帝京大学小学校
実学と結びつき教科横断の軸となる「里山教育」
帝京大学小学校では、「国際社会に貢献できる創造性豊かな人間の育成」を目標に、独自の取り組みを積極的に行っています。その5つの柱となっているのが、「里山教育」「キャリア教育」「英語教育」「レゴ教育」「ICT教育」です。教科横断型の学びにも重要な役割を果たしている「里山教育」について、校長の石井卓之先生と探究科の長谷川椋先生にお話を聞きました。
帝京大学小学校 校長 石井卓之先生のお話
探究の授業(3年生)を取材
帝京大学小学校 校長 石井卓之先生のお話
探究の授業(3年生)を取材

校長 石井卓之先生
帝京大学小学校 校長 石井卓之先生のお話
2022年度に開始した「里山プロジェクト」
現在、本校の校舎がある敷地は、児童数の減少に伴い2009年に廃校となった市立小学校の跡地です。多摩市では里山教育に力を入れていると聞いていましたが、敷地内にある山は放置されたままで、私が着任した2020年には「進入禁止」状態となっていました。かつて使われていた遊具などもありましたが、スズメバチの巣があったり、ハクビシンやタヌキの姿も見られるなど、荒れ果てていたのです。なんとかこの自然を教育に活かせないかと考えましたが、里山づくりは教員の力だけでは難しく、専門家の力を借りる必要があります。そこで多摩市に相談したところ、多摩市の公立小学校で里山づくりに関わったことのある専門家(「一般社団法人まちやま」代表 塚原宏城さん)を紹介していただくことができました。
塚原さんと私の構想をすり合わせてみたところ、5年ぐらいあれば形になるだろうということで、5年分の予算を承認してもらい2022年度から「里山プロジェクト」をスタートさせました。今は塚原さんが中心となって活動していますが、5年経つ頃には専門家にサポートしていただきながら教員が中心となって活動できるようにしていきたいと考えています。自然のない都心の公立小学校で校長をしていた経験もありますが、自然に囲まれた学校の方が子どもは落ち着いて学校生活を送ることができると感じました。里山教育を教育課程にうまく取り込めれば、子どもたちを心豊かに育成できると思っています。本校ではICT教育にも力を入れていますが、デジタルの対極にあるのが自然です。両者を教育に取り込めることができれば面白い教育課程になると考えて、5つの柱の2つに「ICT教育」と「里山教育」を掲げています。
塚原さんと私の構想をすり合わせてみたところ、5年ぐらいあれば形になるだろうということで、5年分の予算を承認してもらい2022年度から「里山プロジェクト」をスタートさせました。今は塚原さんが中心となって活動していますが、5年経つ頃には専門家にサポートしていただきながら教員が中心となって活動できるようにしていきたいと考えています。自然のない都心の公立小学校で校長をしていた経験もありますが、自然に囲まれた学校の方が子どもは落ち着いて学校生活を送ることができると感じました。里山教育を教育課程にうまく取り込めれば、子どもたちを心豊かに育成できると思っています。本校ではICT教育にも力を入れていますが、デジタルの対極にあるのが自然です。両者を教育に取り込めることができれば面白い教育課程になると考えて、5つの柱の2つに「ICT教育」と「里山教育」を掲げています。


PBL型で進める「里山教育」
本校の「里山教育」は、子どもたちがやりたいことを形にしていくPBL型(課題解決型学習)で進めています。子どもたちが「こんなことがしたい」と専門家に相談して、教員はそれをどうサポートするか考えていくのです。教員がゴールを設定する授業とは異なり、児童主体でゴールが見えない状態で進めていくので、初めはどのように進んでいくかわかりませんでした。専門家や造園業者の方に荒れた土地を整理してもらいながら、初年度に6年生が取り組んだことは里山に入るための階段作りです。次年度以降も6年生が何かを残す活動をするようになり、2年目は学校に遊具が少ないということで、竹を使って滑り台を作ってくれました。竹林も整備していかなければ荒れてしまうので、伐採した竹の活用にもつながる活動です。


3年目となった昨年度も遊具ブームが続いていてシーソーを作ってくれましたが、今後も遊具を作ると決まっているわけではなく、子どもたちが他の視点で考えれば違うものを作るでしょう。遊具の安全性などは、専門家が調査して教員もサポートしていますが、昨年度は、子どもたち自身でAR(現実の空間にデジタル情報を重ねて表示する技術)も活用しています。6年生が卒業するまでに設置してお披露目したかったのですが、子どもたち主体でやれるところまでやったので、昨年度は卒業までには間に合いませんでした。これも教員がゴールを決めないというPBL型学習の結果なので、無理に教員が進めて間に合わせることはせずに新年度に設置となりました。

「里山教育」と他教科との連携
1・2年生は生活科の時間に、山からいろいろなものを集めてきてそれを使って「ものづくり」をしています。図工との親和性が高いので、木の枝でアート作品やクリスマスの飾りを作ったり、竹で楽器を作ったりすることもあります。3・4年生は縦割りの宿泊行事を八ヶ岳で行っていますが、里山での活動と八ヶ岳での活動を連動させて、里山という限られた環境からの発展系を大自然の中で実施するのも面白いでしょう。どのようなことができるか見えてきたら、教育課程に位置づけていきますが、大切なのはその時の子どもたちに合ったことを、適した時期に実施することです。同じ学年でも成長度合いや興味・関心は、毎年同じではありません。時期を決めて実施するのではなく、プログラムをいくつか用意しておき、その中から教員がその時の子どもたちに適したものを選ぶというイメージです。
国語では里山で四季の移ろいを見て俳句を作ったりもしていますが、教員が発想できればどの教科でも連携できます。今後の展開に期待して、担当教科と関連づけていけるように教員の力も伸ばしていきたいです。一方で、学校だけで教育する時代は終わったとも感じています。先日は、虫の専門家に2時間授業をしてもらったのですが、虫が苦手な児童も終わる頃には触れるようになったのです。2時間でそこまで変われたことに驚きましたし、教員ではできないことだと実感しました。今後も、専門家をうまく取り入れながら、教育課程を作っていきたいと考えています。
国語では里山で四季の移ろいを見て俳句を作ったりもしていますが、教員が発想できればどの教科でも連携できます。今後の展開に期待して、担当教科と関連づけていけるように教員の力も伸ばしていきたいです。一方で、学校だけで教育する時代は終わったとも感じています。先日は、虫の専門家に2時間授業をしてもらったのですが、虫が苦手な児童も終わる頃には触れるようになったのです。2時間でそこまで変われたことに驚きましたし、教員ではできないことだと実感しました。今後も、専門家をうまく取り入れながら、教育課程を作っていきたいと考えています。


教科教育を実学と結びつける「里山教育」
本校が掲げる5つの柱の1つとして、企業と連携した「キャリア教育」を実施しています。例えば6年生の探究科では、海外で起業家を育成している企業と連携し、バリ島のカカオ農家とZoomでつないで環境問題やフェアトレードについて学んでいます。今年度は、バリ島でコーヒーやカカオの苗木を植林するために子どもたちが校内クラウドファンディングを行い、保護者から約35万円の寄付金を集めました。保護者への返礼品を準備したり、英語科と連携して、自分たちがどのようにしてクラウドファンディングを行ったかなど、英語でバリ島の農家に向けた発表も経験しています。このような「キャリア教育」と、「里山教育」での取り組みをつなげていきたいという構想もあります。

その1つが里山で始めた椎茸栽培です。椎茸農家に栽培方法を教えてもらい、山に「ほだ木」(椎茸菌を植え付けた木)を入れて栽培を始めました。栽培が順調になったら干し椎茸を作って、「帝小ブランド」として売り出したいという夢があります。子どもたちがパッケージをデザインしたり、学校のホームページにECマートを作って販売していけば、いろいろなことが経験できるのです。それが軌道に乗ったら、英語科と連携して海外への販売も行えたらいいなと思っています。いろいろ難しいことがあると思いますが、海外通貨の価値なども学ぶことができるでしょう。
本大学グループ全体として、学んだことを実学に結びつけることができると、子どもたちの力は伸びると考えています。日本の教育は実学に結びついていないので、高校生が理科や数学を学んでも役に立たないと思ってしまうのです。縦軸となっている教科教育に横軸として「キャリア教育」や「里山教育」を通すことで、実社会で活かせる学びになります。「だから勉強が大事」なのだと実感できる体験が循環していくと、子どもたちはどんどん伸びていくのです。
本大学グループ全体として、学んだことを実学に結びつけることができると、子どもたちの力は伸びると考えています。日本の教育は実学に結びついていないので、高校生が理科や数学を学んでも役に立たないと思ってしまうのです。縦軸となっている教科教育に横軸として「キャリア教育」や「里山教育」を通すことで、実社会で活かせる学びになります。「だから勉強が大事」なのだと実感できる体験が循環していくと、子どもたちはどんどん伸びていくのです。

里山を基盤としたサステナブル社会
専門家の協力により、「里山教育」としていくつかのプログラムが整ってきました。2023年度からは、クラブ活動としての「里山クラブ」も実施しています。将来的には、里山を基盤にして、サステナブル社会を学校全体で作りたいと考えています。例えば、校舎を建設する際に理科実験室の前にはビオトープを作りましたが、水は循環していません。いずれは、切り出した竹から竹炭を作って、水質改善に役立てることなども考えています。家庭科室の前にある畑では子どもたちが野菜を栽培していますが、そこに使う肥料として、落ち葉を集めて堆肥化するための活動も始まりました。里山を活用し、校内でいろいろな事が循環したら面白いと考えています。
最近は、公園でも「木に登ってはいけない」などの規制が増えてきました。大自然とは違って管理された学校内の里山では、できるだけ制約のない中で自由に活動させたいと考えています。安全性については、命に関わることは確保していますが、活動する中で多少の怪我は起こりえます。失敗もたくさん経験することで、社会に出てからの失敗を少なくすることができるのです。2022年度に「里山プロジェクト」をスタートさせてから、子どもたちに発想力や創造力が育まれていると感じています。何でもやってみようとする意欲や、自分たちでやろうとする自主性も見られるようになってきました。
今後は、大学とのつながりを強めたいと考えています。これまでも、ボランティアとしてサークルの学生が来てくれることはありましたが、学生単位だと卒業したらつながりが途切れてしまいます。大学の研究室と継続的につながって、環境問題や虫の研究といった多様な刺激を与えることができれば、さらに学びが広がっていくでしょう。小さな刺激がきっかけで、大学でもっと学びを深めたいと思う児童もでてくるかもしれません。系列の大学が近くにあるという強みを活かして、子どもたちがフラッと大学の研究室に行って学んでこられるようなつながりを築き上げていきたいです。
最近は、公園でも「木に登ってはいけない」などの規制が増えてきました。大自然とは違って管理された学校内の里山では、できるだけ制約のない中で自由に活動させたいと考えています。安全性については、命に関わることは確保していますが、活動する中で多少の怪我は起こりえます。失敗もたくさん経験することで、社会に出てからの失敗を少なくすることができるのです。2022年度に「里山プロジェクト」をスタートさせてから、子どもたちに発想力や創造力が育まれていると感じています。何でもやってみようとする意欲や、自分たちでやろうとする自主性も見られるようになってきました。
今後は、大学とのつながりを強めたいと考えています。これまでも、ボランティアとしてサークルの学生が来てくれることはありましたが、学生単位だと卒業したらつながりが途切れてしまいます。大学の研究室と継続的につながって、環境問題や虫の研究といった多様な刺激を与えることができれば、さらに学びが広がっていくでしょう。小さな刺激がきっかけで、大学でもっと学びを深めたいと思う児童もでてくるかもしれません。系列の大学が近くにあるという強みを活かして、子どもたちがフラッと大学の研究室に行って学んでこられるようなつながりを築き上げていきたいです。


探究の授業(3年生)を取材
探究科 長谷川椋先生のお話
3年生は、落ち葉を集めて腐葉土にするために竹でコンポストを作る作業をしています。今日行っているのは、外側の枠を作るために竹を切って、枝払いをする作業です。来週は、枝を落とした竹を組んで容器の壁を作ります。通常、図工の授業などではノコギリを扱うのはもう少し上の学年ですが、本校では2年生の生活科で、竹の楽器を作る際にノコギリの使い方も学びました。2年生のときは教員と一緒に切る作業を行いましたが、その経験で慣れたので今年は児童1人でノコギリを扱っています。
切り終わった竹は校庭に移動させて、校庭に隣接した山の斜面にコンポストを設置する予定です。竹の容器ができたら、落ち葉をどんどん集めて入れていきます。できた肥料は、校内の畑で使ったり、1・2年生は教室前のプランターで花や野菜を育てているので、上級生として下級生のために役立てようという取り組みにもつなげていきたいです。
切り終わった竹は校庭に移動させて、校庭に隣接した山の斜面にコンポストを設置する予定です。竹の容器ができたら、落ち葉をどんどん集めて入れていきます。できた肥料は、校内の畑で使ったり、1・2年生は教室前のプランターで花や野菜を育てているので、上級生として下級生のために役立てようという取り組みにもつなげていきたいです。

探究科 長谷川椋先生

児童の感想(3年生)
今日は、肥料を作るための入れ物に使う竹を切りました。竹の枝を切る時に、枝が顔の高さにあると前が見にくいので少し難しかったです。2年生のときにノコギリを使って竹で楽器を作ったので、ノコギリを使うのは慣れました。ギコギコと手を動かして竹を切ったり、みんなで作業するのが楽しいです。卒業した6年生が作ってくれた竹の滑り台は、校庭でサッカーをした後などに遊んでいます。虫が好きなので、カブトムシやクワガタなどが観察できる山が近くにあるのはいいなと思います。